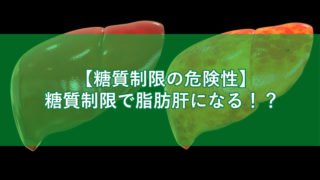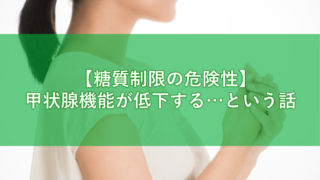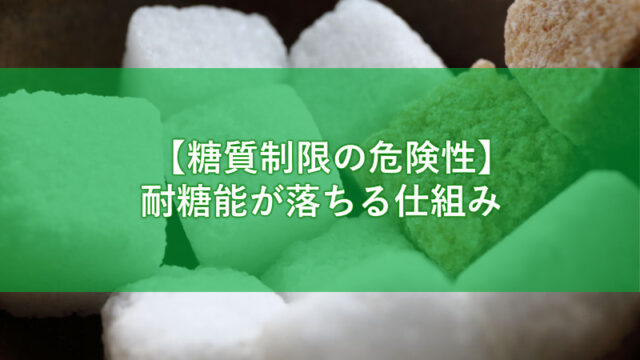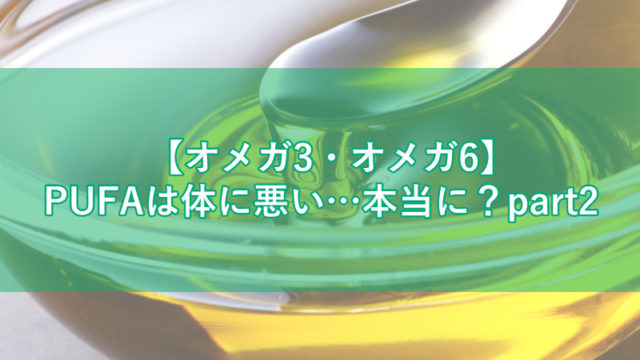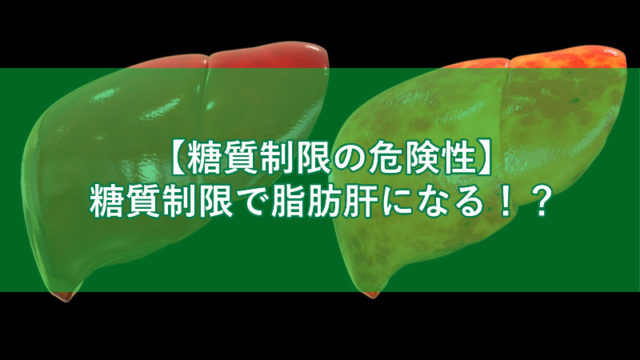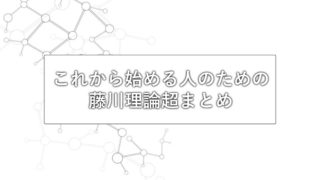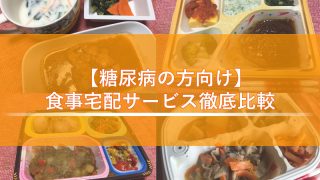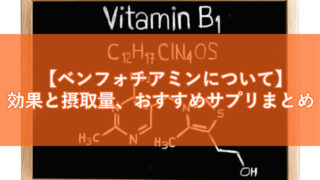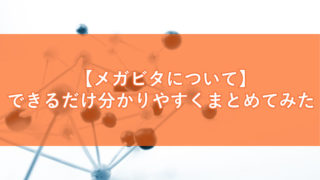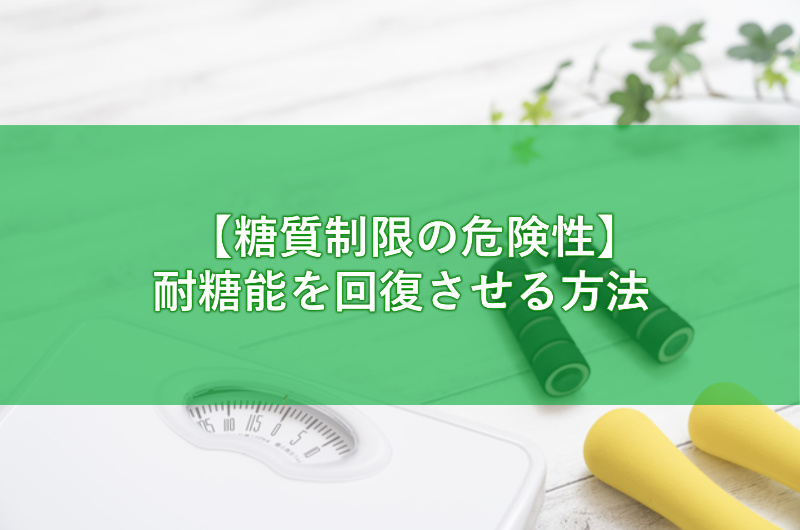
前回までで耐糖能が落ちる仕組みを見てきました。ということで今回はそれを元に解決策を模索してみます。
といっても、実験や研究があるわけではなく、こういう仕組みならこれで解決するんじゃない?という提案みたいなものです。これで耐糖能が回復するとは限らないのであくまで参考程度に。
耐糖能を戻すための解決策
耐糖能が悪化する仕組みで出てきたのは
- 脂質による筋肉のインスリン抵抗性増大
- 遊離脂肪酸による膵臓のβ細胞障害
- オートクリンによるβ細胞減少とα細胞増大
- 栄養素不足
この4つ。4つ目の栄養素に関してはメガビタ情報が中心です。
一つ一つ解決策を見ていきましょう。
1,脂質による筋肉のインスリン抵抗性増大
慢性的に糖不足の状態だと骨格筋が糖代謝している場合ではない(赤血球や脳にグルコースを回したい)ので、骨格筋のインスリン抵抗性が上がる
問題になるのは慢性的な糖不足という部分。なので解決策としては極端な糖質制限は避けるということになりそうです。
ただどのレベルが極端な糖質制限になるのかは人それぞれで難しいところ。前々回記事であったように、スーパー糖質制限で耐糖能が改善したという話(記事内 B)糖尿人の冒頭)もあるので、1食20g以下でも問題ない人はいるようです。
2,遊離脂肪酸によるβ細胞傷害
β細胞環境下の遊離脂肪酸濃度が上昇すると、とりわけ飽和脂肪酸であるパルミチン酸によって炎症が起こり、それによって膵臓β細胞が死滅していく(PUFAが原因という説もある)
これに関しては遊離脂肪酸濃度が高い状態が問題なので、前回すでに書いたように、運動して遊離脂肪酸をエネルギーとして燃やすのが正解。それと肥満の場合も遊離脂肪酸濃度は高くなるので痩せるのも大事。運動しましょう!
それ以外の方法だと山本義徳先生の記述から。
ですが糖尿病なのでインスリンの働きが悪いとHSLが活性化し、遊離脂肪酸が増加するのです。このとき運動をして遊離脂肪酸をエネルギーとして燃やすことができれば良いのですが、運動をせずにカロリーを消費しないでいると、血中の遊離脂肪酸は高いままということになります。
つまり肥満でもなく、運動を日常的に行っているのなら、遊離脂肪酸が恒常的に高まることもなく、インスリン抵抗性を引き起こすようなことはありません。しかしバルクアップなどで長期に渡ってハイカロリーを摂取していたり、怪我などでトレーニングをおこたっていたりすると、問題になる可能性もあります。
そのような場合は論文にあったとおり、NACのような抗酸化物質を摂取することで、一つの対策となります。
また紅花油や菜種油、大豆油はインスリン抵抗性を高めたが、魚油を摂取した場合は肥満も耐糖能の悪化も生じなかったとするマウスでの報告があります。なおシソ油やパーム油では体重は増加するものの、耐糖能は悪化していません。
引用:ダイエットの理論と実践
ということで、NACといった抗酸化物質を摂るのも対策となるようです。
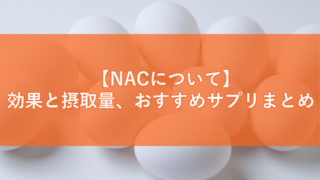
またPUFAが原因と仮定するなら油の種類で改善するかもしれません。上であるように『オメガ6の多い植物油(紅花油、菜種油、大豆油)はインスリン抵抗性を高めた』とあるので、調理油にはオメガ6(リノール酸)の割合が低いオリーブオイル、バター、ココナッツオイルを使う。
ちなみに揚げ油もオリーブオイルがいいでしょう。(下記リンクは精製オリーブ、トウモロコシ、大豆、ひまわりの油の劣化を調べたもの。オリーブが最も劣化しなかった)
まぁそもそも揚げ物はなるべく減らしたいですが。
3,オートクリンによるβ細胞減少とα細胞増大
β細胞は自身が分泌するインスリンによって機能・増殖を調節している。そのためインスリン分泌が減り糖新生が亢進すると、脱分化してα細胞に変化し、グルカゴンを分泌するようになる
これも糖新生が亢進するのが問題になるので、糖新生が活発になるほどの糖質制限はやらない。つまり極端な糖質制限は避けるということになりそうです。1つ目と一緒ですね。
ただこれも難しいところで、中途半端に糖質制限をした場合、脂肪の摂取量が少なくケトン体の材料が足りなくなります。結果エネルギー不足になるので糖新生が亢進します。
なので減らすのは糖質か、脂肪か、どちらかだけ、エネルギー量(総カロリー)は減らさないように注意が必要です。(もちろんダイエット時は除く)
4,栄養素不足
最後に栄養素について。これも引用を。
糖質の摂取量を増やすときには、同時にこれらを回復させてやることが重要です。
そのためには、ケトーシスを狙う初期プログラムと同じように、以下のようなサプリメンテーションを行います。
●リバウンドを防ぐサプリメンテーション
- αリポ酸を多めに摂取。できればRリポ酸として毎食後に200~300mgずつ。
- アルギニンの摂取。一日に6~10gほど。
- クロムのサプリメントを朝食後と夕食後に200~300μgずつ。
- 亜鉛が不足しないように注意。
- トレーニングをしっかり行う。
- シナモンパウダーを一日小さじ2杯。
- バナバ茶を飲む
- その他、マグネシウムなども。
引用:ダイエットの理論と実践
マグネシウム、亜鉛、αリポ酸、このあたりは記事にしてるのでどうぞ。
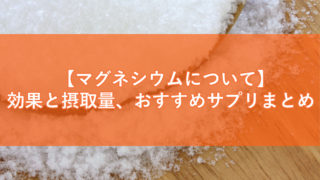
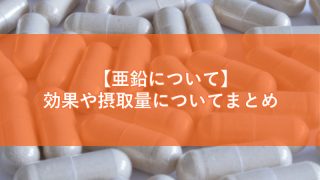

アルギニン、クロムはまた後日調べてみます。シナモンパウダー、バナバ茶も。
マグネシウムと糖尿病の関係は色んな報告があって、糖質制限で耐糖能が落ちるのはマグネシウム不足じゃない?という指摘もあります。そば、バナナ、芋あたりはマグネシウムを多く含むものの糖質制限で避ける食材なので、マグネシウム不足は割とあるんじゃないかな?
また糖質制限だと相対的に肉の量が増えて、カルシウム過多でマグネシウム不足にもなりやすいので、マグネシウムはかなり意識しておかないと不足しやすいと思います。
解決策まとめ
というわけでまとめてみると…
- 運動して遊離脂肪酸濃度を下げる
- 太っている場合は痩せる
- 極端な糖質制限は避ける=緩やかな糖質制限にする or ケトジェニックレベルの糖質制限は短期間に抑える
- 植物油を避ける(オリーブ、バター、ココナッツオイルに変える)
- NAC
- マグネシウム
- 亜鉛
- αリポ酸
- クロム
- アルギニン
といったところ。
ちなみに痩せる段階では脂質制限より糖質制限の方がメリットが大きいです。継続のしやすさ、ケトン体(主にβヒドロキシ酪酸:BHB)の健康効果を考えると、短期的に厳しく制限するのは十分ありだと思ってます。(その後徐々に糖質量を戻していく感じ)
僕の場合は、筋トレ後は糖質摂取、それ以外は糖質制限(緩めで主食なし)が基本。油は基本オリーブオイル。NAC、亜鉛、αリポ酸をサプリで摂取、マグネシウムはエプソムソルトからも、というようにしています。緩めなのでそもそも耐糖能を気にする必要はなさそうですが。
本当に耐糖能は戻るのか?
ここまでまとめた内容はあくまで理論で、データがあるわけじゃありません。無責任なようですが、ここは自分で試すしかないですね。
こういった方法で自分自身で試してみてください。
江部先生のデータ(記事内HOMA-βの値)を見る限り、分泌能は回復しそうなので、糖尿病だから絶対戻らない、ということもなさそうです。もっと研究が進んでいけば、糖尿病も治る病気の一つになっていくのかもしれません。
最後に
今回は耐糖能を調べてきたんですが、糖質制限が危険であるというのはちょっと行き過ぎな主張だなぁと個人的に思います。
耐糖能含めまだまだ分かっていないことがあって、もしかしたら危険な側面はあるかもしれない。ただ糖質の種類や量もあるし、糖以外の要素も確実に関係してくるし、何より逆の側面、合併症を防いだり、ケトン体に健康効果があるという点を無視してるよなぁと。
ただ注意点があるのは確かなので、糖質制限の反対意見は今後もチェックしていきます!