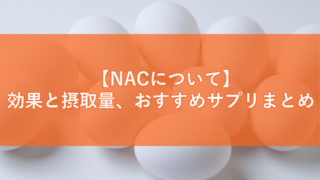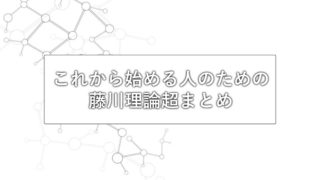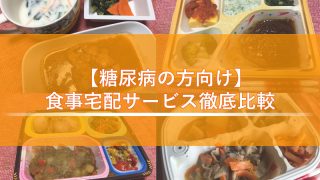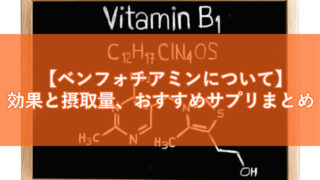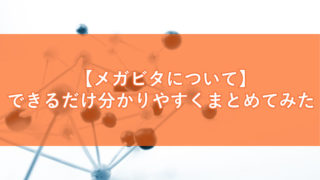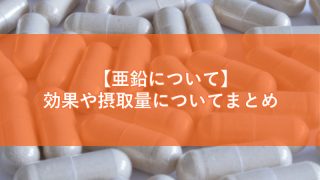糖尿病になると食事に気を遣わなくてはいけません。中には避けたほうがいい食品もたくさんありますよね。
果物はどうなのでしょうか?糖質が含まれているのであまり良くないイメージがあるかもしれません。ですが、果物は量さえ気をつければ糖尿病の人でも食べることが出来ます。1日の目安量やおすすめの種類、時間帯について見ていきましょう。
糖尿病でも果物を食べて大丈夫?
果物には糖質が含まれています。ですから血糖値を上げてしまい、糖尿病の人には良くない、というイメージがあるかもしれません。
糖質が含まれているのは事実ですが、果物には他にもたくさんの栄養素が含まれています。毎日の栄養バランスを整えてくれるのにも役立ってくれるので量を守って食べるのがおすすめです。
果物に含まれる栄養素
果物の種類にもよりますが、果物には不足しがちな栄養素がたくさん含まれています。
- 食物繊維
- βカロテン
- ビタミンC
- ビタミンE
- カリウム
など。
食物繊維は糖の吸収を穏やかにする働きがあります。ですから食後の血糖値の急上昇を抑えてくれるんですよ。糖質も含まれていますが、食物繊維なども含まれていますし、絶対食べてはいけないという訳ではないのです。
ただし、食べる場合でも量には気をつけなくてはいけません。食べる量については後ほどご説明します。
果物の糖分に対する考え方
 果物には果糖、ショ糖、ブドウ糖といった糖質が含まれています。糖質の割合は果物の種類や、完熟度合いによって変わってきます。甘い果物は糖質量が多いと考えましょう。
果物には果糖、ショ糖、ブドウ糖といった糖質が含まれています。糖質の割合は果物の種類や、完熟度合いによって変わってきます。甘い果物は糖質量が多いと考えましょう。
果物に含まれる果糖は、ブドウ糖に比べると腸での吸収が穏やかです。また、果糖はブドウ糖よりも早く代謝されるためエネルギーに変換されやすいといわれています。つまり、同じ糖分でも米やパンなどに比べると体に吸収されるスピードは比較的ゆっくりになるということになります。
諸説ありますが、果物の糖分を気にして摂取しないよりも、果物の食物繊維やビタミン、ミネラルを摂取するほうがいい、と考えている医者や研究者は多いです。
おすすめの果物と避けたほうがいい果物は?
 先ほどもお話しした通り、果物は種類によって糖質量などの栄養素が異なります。糖尿病の方におすすめの果物と避けたほうがいい果物を紹介しますね。
先ほどもお話しした通り、果物は種類によって糖質量などの栄養素が異なります。糖尿病の方におすすめの果物と避けたほうがいい果物を紹介しますね。
おすすめの果物
果物は皮を含めて丸ごと食べるのがおすすめです。皮には食物繊維が多く含まれています。中でもおすすめなのはブルーベリーです。ハーバード大学の研究では、「ブルーベリーを週に3回食べていた人は糖尿病の発生率が33%低下した」というデータがあります。
日本語での解説:リンゴやブドウなど果物が糖尿病リスクを低下 週3回が効果的
皮ごと食べられるので食物繊維が豊富な上、ビタミンA,ビタミンC,アントシアニン、フラボノイドなどが豊富に含まれています。
他にはみかん、グレープフルーツなどの柑橘類もおすすめです。内袋も一緒に食べたほうが食物繊維をたくさん摂取できますよ。甘すぎる果物よりも酸味がある果物を選ぶと糖質を抑えられます。
なるべく避けたい果物は?
100gあたりの果物に含まれる糖質量は以下の通りです。
| 果物 | 100gの目安 | 糖質量 |
|---|---|---|
| ぶどう巨峰 | 8~10粒 | 14g |
| バナナ | 中1本 | 12.9g |
| りんご | 小1/2個 | 12.1g |
| マンゴー | 小1個 | 11.2g |
| さくらんぼ | 30粒 | 10.9g |
| ブルーベリー | 80~100粒 | 10.8g |
| キウイフルーツ | 中1個 | 9g |
| 桃 | 大1/2個 | 8.5g |
| パイナップル | 7切れ | 8.3g |
| グレープフルーツ | 小1/2個 | 5.4g |
| いちご | 7~8粒 | 3.9g |
参照元:かわるpro | 果物に含まれる糖質の種類
糖尿病の方は糖質が少ない果物を選ぶといいでしょう。ただし、糖質量の多いぶどうやりんごは皮ごと食べることもできるので、一概に悪いとは言い切れません。先ほど、糖尿病の予防に効果があったとご紹介したブルーベリーも糖質量は低くはありませんよね。
糖質の摂取量が少ないに越したことはないですが、どうしてもNGという訳ではないんです。生で食べる場合、目安量さえ守っていれば食べてはいけないという果物はありません。(目安量は次の章でご紹介しますね。)
ですが、缶詰、ドライフルーツ、フルーツジュースなど果物を使用した加工品は糖尿病の方におすすめできません。加工品は生の果物よりも糖質が多く、ビタミンCなどの栄養素は減少しています。
特にフルーツジュース(野菜ジュースも同様)に含まれているのは果汁のみです。食物繊維が含まれず糖質が多く、血糖値が急上昇してしまう可能性があります。
果物を食べるなら1日の目安量はどのくらい?
 糖尿病の方でも、果物はおすすめの食べ物です。とはいえ、量には気をつけなくてはいけません。
糖尿病の方でも、果物はおすすめの食べ物です。とはいえ、量には気をつけなくてはいけません。
健康な人の場合、果物の1日の目安摂取量は200g。ですが、糖尿病の方は1日1単位(80kcal)を目安にするとよいでしょう。200g食べられる果物もあれば、それ以下のものもあります。
目安量は下記の表を参考にしてください。
| 果物の種類 | g | 目安 |
|---|---|---|
| みかん | 200 | 中2個 |
| ぶどう | 150 | 巨峰10~15粒 |
| グレープフルーツ | 200 | 小1個もしくは大1/2個 |
| 桃 | 200 | 大1個 |
| 柿 | 150 | 中1個 |
| さくらんぼ | 150 | 50粒 |
| バナナ | 100 | 中1本 |
| キウイフルーツ | 150 | 小2個 |
1種類の果物だけでなく、組み合わせてもOKです。1日1単位を超えない範囲で組み合わせてみてくださいね。
果物を食べるタイミングの目安は?
果物を食べるおすすめのタイミングは朝です。朝は基礎代謝も高いためエネルギーになりやすいんです。果物は食後の糖質の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を抑制する働きがあります。言い換えればゆっくり血糖値が上がるのです。
夕方から夜にかけて摂取すると、寝る頃に血糖値が上がってしまいます。ですから、夕方以降に果物を食べるのはやめましょう。
間食として食べるというのもOKですが、間食自体がおすすめできる行為ではありません。「間食をするならお菓子よりも果物がマシ」という程度です。できるなら果物は食事と一緒に摂取した方がよいですよ。

まとめ
果物には糖質が含まれていますが、食物繊維やビタミン、ミネラルも豊富です。量を守れば糖尿病の方にもおすすめの食べ物ですよ。
1日の目安量は1単位(80kcal)です。果物の種類によって量は異なりますので注意して食べるようにしてください。皮に食物繊維が豊富に含まれています。よく洗って皮ごと食べるのがおすすめです。
生の果物でどうしてもNGという種類は特にありません。ですがドライフルーツ、缶詰、フルーツジュースなどは生の果物とは栄養分が異なるためおすすめしません。
目安量を守って生の果物を摂取するようにしましょう。特に朝食と一緒に食べるのがおすすめです。