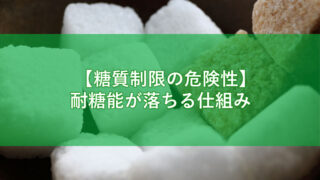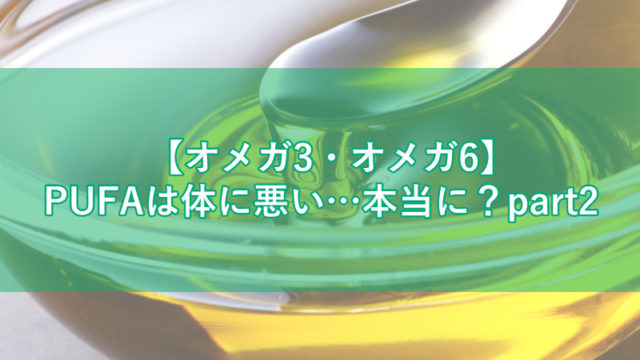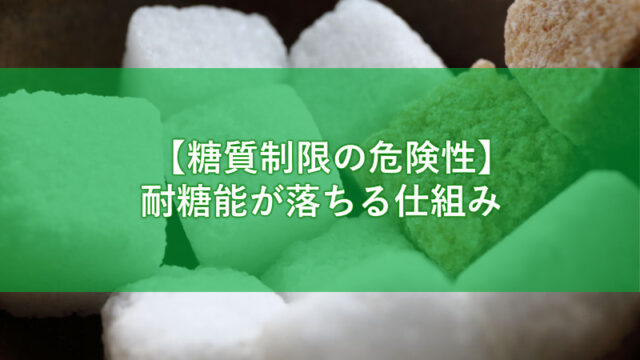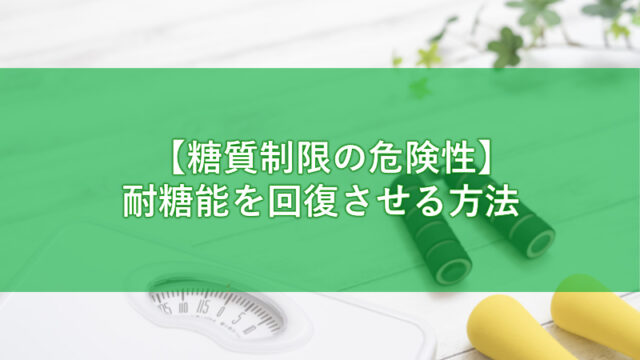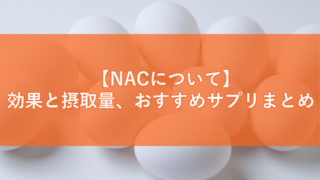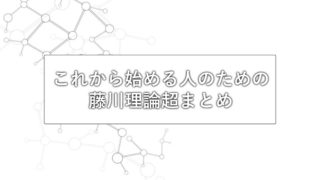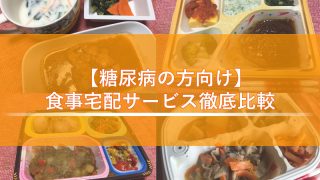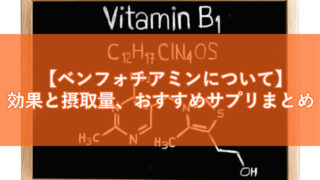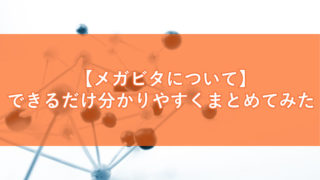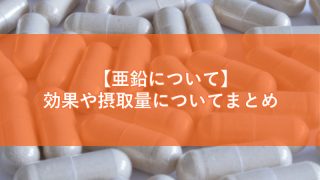糖質制限が危険であるとされる理由に『耐糖能が落ちる』というものがあります。今回は耐糖能は本当に落ちるのか?という部分を調べてみました。
そもそも耐糖能とは?
糖(グルコース)を処理する能力のことを耐糖能といい、糖負荷試験(OGTT:oral glucose tolerance test)によって判断される。
糖負荷試験は75gのブドウ糖を飲んで、その後の血糖値の推移を見るわけですが、空腹時血糖値やピークの値が以前より高くなっていれば耐糖能は落ちたと言えます。また、
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科准教授の西村理明氏の研究によれば、
1)耐糖能正常者24名の食後血糖値のピークは、40分から50分
2)HbA1c8%未満の患者はおおむね1時間から90分の間にピーク
3)HbA1cが8%を超える患者では2時間後にピークです。
ピークが、後にずれるほど、耐糖能が良くないと言えるようです。
ということで、ピークが後にずれた場合も耐糖能が落ちたと言えそうですね。
耐糖能をもう少し詳しく見てみる
血糖値で判断されるのが耐糖能なんですが、じゃあ血糖値が何によって決まるのか?もう少し詳しく分解してみましょう。(後にも繋がる話です)
耐糖能=グルコース感受性×インスリン感受性
血糖値はこの2つの要因で決まってくるとされています。
グルコース感受性について詳しくは、しらねのぞるば先生が触れています。血糖値が上がり始めた時に、すぐにインスリン分泌が始まるかどうか?を表す指標です。
グルコース(糖)を摂ると血糖値は上がり始める…すると、すぐにインスリンが分泌されると思ってたんですが、どうやらそういうわけではないというのが『グルコース感受性』に関する話。
日本人はそもそもインスリン分泌量が少ないという話がありますが、さらにグルコース感受性も低いのでは?というのが以下の記事。
もう一つのインスリン感受性は
インスリン感受性=インスリン分泌能×インスリン抵抗性
ここではこう分解して考えてみます。
分泌能はその名の通り、膵臓のインスリンを分泌する能力。抵抗性は糖を取り込む細胞(肝臓、骨格筋など)のインスリンの効きにくさ。(インスリン抵抗性が高い=より効きにくい)
そうすると、耐糖能が落ちるというのは
- グルコース感受性が低くなる
- インスリン分泌能が低くなる
- インスリン抵抗性が高くなる
このどれか、もしくは複数で耐糖能が落ちると言えそうですね。
ただ実際にはグルコース感受性は未知の分野なので、2と3番、インスリン分泌能が低くなるか、インスリン抵抗性が高くなる、もしくはその両方で耐糖能が悪化すると言えます。
さて、話を戻して糖質制限で耐糖能は落ちるのかどうかを見ていきましょう。
糖質制限で耐糖能は落ちるという話
基本的に糖質制限をすると耐糖能は落ちると言われています。糖を摂らないと糖を処理する能力は落ちる。筋肉を使わなければ衰えるのと同じ理屈ですね。
いくつか研究も挙げられていて分かりやすいと思ったのが以下の記事。
個人のブログではあるんですが、引用も多数あって信憑性もあるので一度読んでみてください。
また山本義徳先生も著書の中で耐糖能について触れています。
また糖質制限によって「耐糖能」が低下します。これはブドウ糖を処理する能力のことで、糖質を摂取したあとインスリンが正常に分泌されて血糖値が低下するかどうかを示したものです。
またインスリンと拮抗するグルカゴンやカテコールアミンの影響も考えられますが、糖質を摂取していないとインスリンの分泌能力が衰え、インスリン感受性も低下するというわけです。
『糖質制限の問題は』という項で触れられています。
糖質制限で耐糖能が落ちるのは割とポピュラーなようです。
耐糖能が落ちるとは限らないという話
ということで、糖質制限で耐糖能は落ちるんだ…と思いきや、逆の意見もあります。
【厳格な糖質制限を勧めない本などでは、
厳格な糖質制限を長い間すると、たまに糖質をとっただけで
かえって大きなスパイクが起きると書いてある】この現象は、生じる人と生じない人がいます。
糖質制限を実践したからといって、必ず耐糖能が落ちるわけではないという主張。
実際に以下の記事を読む限り、江部先生本人のインスリン分泌能は少し改善(HOMA-βの値が正常値に近づいている)していて、
2型糖尿病の診断基準をしっかり満たした人が、
1年間のスーパー糖質制限食実践で血糖値もHbA1cも正常値となり、
試しに白ご飯を一人前(糖質量は55g)摂取しても、
血糖はピーク140mg/dlを超えなくなった例もあります。
というような記述もあります。以下がその記事。
ただなぜ耐糖能が落ちる人と落ちない人がいるのかについては、
私見ですが、これは基礎分泌インスリンは普通に出しているけれど、
追加分泌インスリンをあまり出す必要がない糖質制限食を続けていた場合には、
糖質摂取に対して、β細胞が準備ができていない状態であった可能性があります。前もって、150g/日以上の糖質を3日間摂取することで準備を整えてから検査をすると、
β細胞の準備ができているので、
もともと正常型だった人なら耐糖能がデータ的に普通に戻ると考えられます。スーパー糖質制限食実践でβ細胞は休養できていて、
なおかつ血糖コントロール良好ですので、
高血糖によりβ細胞が障害されている可能性はありません。
従って、β細胞のインスリン分泌能力も準備さえ整えば、
正常に作用すると考えられます。
つまり、正常人が糖質制限中にいきなり糖質摂取したとき、
一見耐糖能が低下したようなデータが出ることがありますが、
これは本当にβ細胞が障害されて耐糖能が落ちたのではないので、
心配ないということです。
糖質制限食実践者においては、食後高血糖によるβ細胞の障害はないので、
本当にインスリン分泌能が低下するということは考えられません。
『可能性があります』『考えられます』ということで実際の研究やデータは特にないようです。(ここは筋トレの王城さんに指摘されていましたね)
ちなみに大幅に改善した例もあるようです。それが以下。
また、以下の記事は妊娠糖尿病での話なので少し特殊かもしれませんが、出産後に境界型と診断されたものの、糖質制限で耐糖能が回復した例です。
ちなみにしらねのぞるば先生も耐糖能は悪化してはいないようです。(改善したとは言えないものの悪化はしていないという結論)
問題になるのは『糖質制限』の定義
さて、ここまで見てきて結局どっちなんだ!?って混乱している人もいそうですが、重要なのは『糖質制限』の定義。
耐糖能が落ちたのは『厳しい糖質制限』。逆に耐糖能は落ちない、回復したというのは『緩い糖質制限』のケースが多いですね。
上の記事で取り上げられているこの実験の糖質制限は炭水化物の割合はたったの2%。(たんぱく質15%、脂質83%)
また山本義徳先生も
海外における低糖質食の研究を見ると、大半がカロリー比にして糖質は全体の10-20%以下となっています。この場合、「ケトーシス」になり、糖質ではなくケトン体を主なエネルギー源としています。ここまで糖質を減らす場合、これは「ケトジェニックダイエット」とも呼ばれます。
これを耐糖能の話の直前に指摘しています。
逆に改善したという江部先生の記事例では『ゆるやかな糖質制限』。量に関する記述はないですが、スタンダード、もしくはプチ糖質制限ぐらいかと思います。
『糖質制限食』の3パターン
一、スーパー糖質制限食は三食とも主食なし。効果は抜群で早く、一番のお薦め。
1回の食事の糖質量は20g以下。
二、スタンダード糖質制限食は、一日一回(朝か昼)少量の主食あり。夕食は主食抜き。
三、プチ糖質制限食は夕だけ主食抜き。朝と昼は少量の主食あり。
嗜好的にどうしてもデンプンが大好きな人に。
スタンダード、プチが分からない人用に一応補足。
ただ、上で紹介したようにスーパー糖質制限を1年間実践して耐糖能が改善した例もあるそうなので、単純に糖質の制限量だけで耐糖能が悪化する、しないは言い切れなさそうです。
他の要素(栄養素、筋肉量、活動量など)も関わってきそうですが、ひとまず緩やかな糖質制限で耐糖能が落ちたという話は僕が探した限り見当たらなかったので、耐糖能が気になる場合は厳しい糖質制限を避ける、もしくはあまり長期では厳しくやらないようにすると良さそうです。
まとめ
ということで今回は耐糖能について見てきました。糖質制限で耐糖能は落ちると思ってたんですが、どうもそう単純な話ではないようです。
それと今回落ちるかどうかを見てきたんですが、回復するかどうかも重要になってきます。仮に耐糖能が一時的に落ちたとしても、回復するなら特に問題ないはずですよね。
次回は耐糖能が落ちる仕組みを深堀りしていきます。まだまだ分かっていないことだらけとはいえ、原因の検討が付けば解決策も見えてくる…はず。