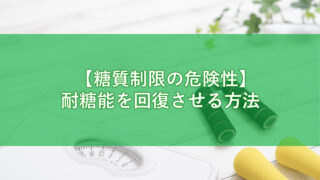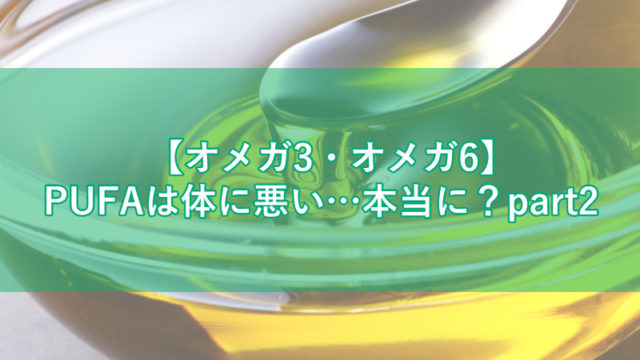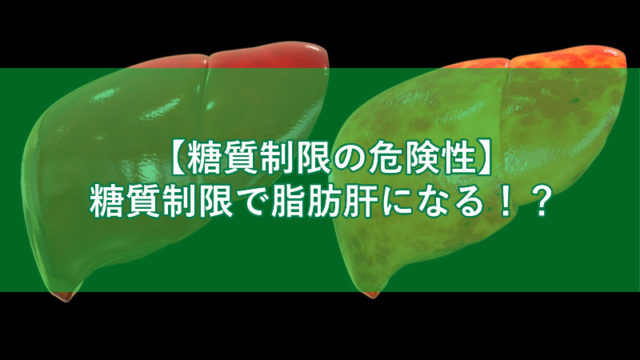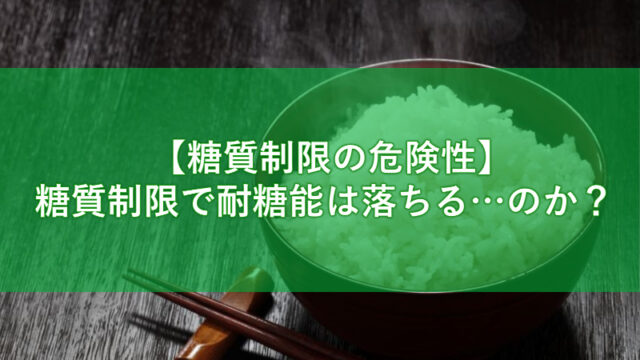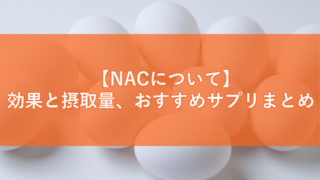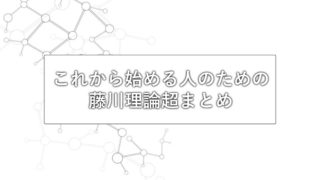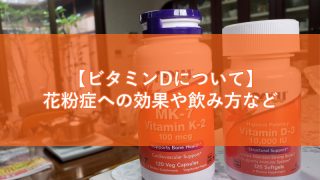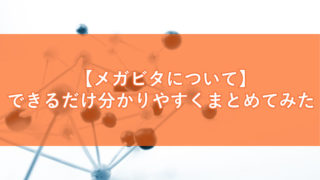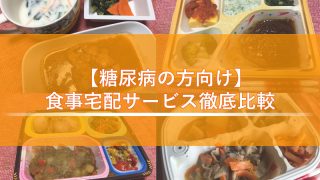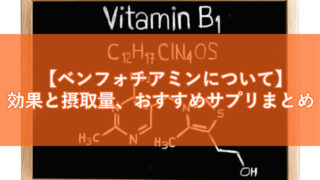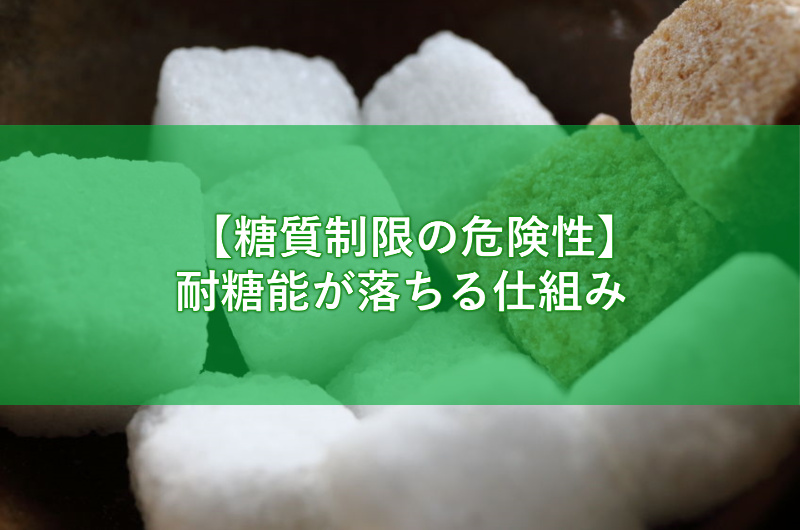
糖質制限によって耐糖能が低下する場合がある、というのは前回の記事で示した通り。今回は耐糖能がなぜ低下するのか?という作用機序の部分を調べてみました。
全て解明しているわけではないものの、仕組みが分かれば解決策も見えてくるかも?ということで参考に。
耐糖能をおさらい
前回の記事で書いたように、
耐糖能=グルコース感受性×インスリン感受性
(インスリン感受性=インスリン分泌能×インスリン抵抗性)
ということで、
耐糖能=グルコース感受性×インスリン分泌能×インスリン抵抗性
耐糖能はこの3つが要因として関わってくるという話でした。なので、
- グルコース感受性が低くなる
- インスリン分泌能が低くなる
- インスリン抵抗性が高くなる
この3つそれぞれ、または複数が重なって耐糖能が落ちることになります。
ただグルコース感受性は未知の分野なので、話として出てくるのはインスリン分泌能が低くなるorインスリン抵抗性が高くなる、というこの2つ。
それを踏まえて耐糖能が落ちる!と言ってる仕組みを取り上げてみましょう。
耐糖能が落ちる仕組み
主に3つの主張があったので取り上げてみます。
- 脂質による筋肉のインスリン抵抗性増大
- 遊離脂肪酸による膵臓のβ細胞障害
- オートクリンによるβ細胞減少とα細胞増大
一つずつ見ていきましょう。
1,脂質によって筋肉のインスリン抵抗性が起こる(抵抗性の増大)
詳しくは下記記事を読んでもらうとして、
簡単にまとめるなら
慢性的に糖不足の状態だと骨格筋が糖代謝している場合ではない(赤血球や脳にグルコースを回したい)ので、骨格筋のインスリン抵抗性が上がる
という仕組み。骨格筋はケトン体からエネルギーを取り出せばいいから、インスリン抵抗性を上げて糖を代謝しにくくする、という仕組みですね。
2,遊離脂肪酸によるベータ細胞の傷害(分泌能の低下)
続いてはこの記事。
簡単にまとめると、
β細胞環境下の遊離脂肪酸濃度が上昇すると、とりわけ飽和脂肪酸であるパルミチン酸によって炎症が起こり、それによって膵臓β細胞が死滅していく
という仕組み。
これはPUFAが原因であるとする説もあります。
そして、膵臓のベータ細胞に炎症を引き起こして破壊する最大の原因は、プーファ(PUFA:多価不飽和脂肪酸、オメガ3&6)であることがすでに報告されています。実際に、破壊された膵臓を調べると、プーファが酸化して形成されたアミロイドタンパク質が蓄積しています。
情報源として挙げられていた研究。
翻訳も駆使してみたんですが、全文読めるわけではないので、どこにそういう内容があるのかよく分かりませんでした…。ただどちらの主張も根拠になるのはマウス実験のようで、ヒトでは当てはまらない可能性もあります。(もちろんこの通りの可能性もあります)
遊離脂肪酸に関する補足
共通して『遊離脂肪酸が高いと問題になる』ということですが、
ところで高脂肪食にすると、血中の遊離脂肪酸もそれに伴ってレベルが上昇するのでしょうか。脂肪を消化吸収すれば当然そうなりそうなのですが、実はインスリンが正常に分泌されているヒトでしたら、食後でも血中の遊離脂肪酸は正常値範囲内に収まるのです。
基本的に食後に上昇するのは「中性脂肪」であり、遊離脂肪酸はあまり上昇しません。むしろインスリンの働きにより遊離脂肪酸から中性脂肪がつくられて脂肪組織に送られるため、普通の人は食後の遊離脂肪酸は低下する傾向にあります。
ただしインスリンの働きが悪い2型糖尿病の人は、そうなりません。また肥満でインスリンの働きが悪くなっていても、食後の遊離脂肪酸は上昇してしまうことがあります。
引用:ダイエットの理論と実践
ということで、特に肥満の人や2型糖尿病の人はちゃんと運動をしてエネルギーとして消費するのが重要になりそうです。
3,オートクリンによるβ細胞の減少とα細胞の増大(分泌能の低下)
3つ目はこの記事。
記事内で紹介されている実験。
これは
β細胞は自身が分泌するインスリンによって機能・増殖を調節している。そのためインスリン分泌が減り糖新生が亢進すると、脱分化してα細胞に変化し、グルカゴンを分泌するようになる
ちょっと分かりにくいかもしれないので簡単にまとめるなら、
『インスリン要らないならβ細胞もあんまり要らないでしょ?だったらグルカゴン分泌するα細胞増やした方がいいよね、糖新生もっと頑張らないと!』
という感じ。
これも理にかなっているし有り得そうです。(ただ一応補足しておくとマウス実験になります)
4,他に考えられる要因
以上3つが主に挙げられていたんですが、個人的には糖以外の要素も大きく関わっていると睨んでいます。
直接関わってきそうなのは亜鉛、マグネシウム。亜鉛は分泌能に、マグネシウムは抵抗性に関わってきます。このあたりはそもそも不足していると言われている上、糖質制限で食材が偏ることでさらに不足する可能性は十分あるんじゃないかと。
まとめ
ということで耐糖能が落ちる仕組みというのを見てきました。ただ全てが解明されているわけではないので、また別の要素が関わってくるかもしれません。研究が進めば明らかになっていくでしょう。
それと補足しておくと、上で解説したのは全てマウス実験がベースのようなので、ヒトでは当てはまらない可能性もあります。(マウスに脂質を静脈注射してたりします。)誰かが言ってるから、というだけで鵜呑みにせず、何を根拠に言ってるのかまで把握していきたいですね。難しいですが。
また糖質制限といっても、どれだけ減らせば耐糖能が落ちるのかは分からないし、個人差もあるはずです。今回挙げたものはケトとも言えるものが多いので、その点でも注意が必要です。
さて、これを踏まえた上で次回、下がった耐糖能を回復させる方法を模索してみます。