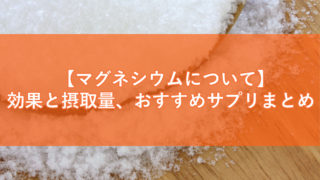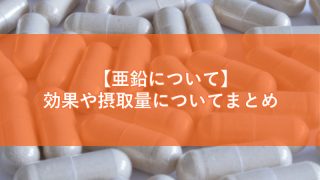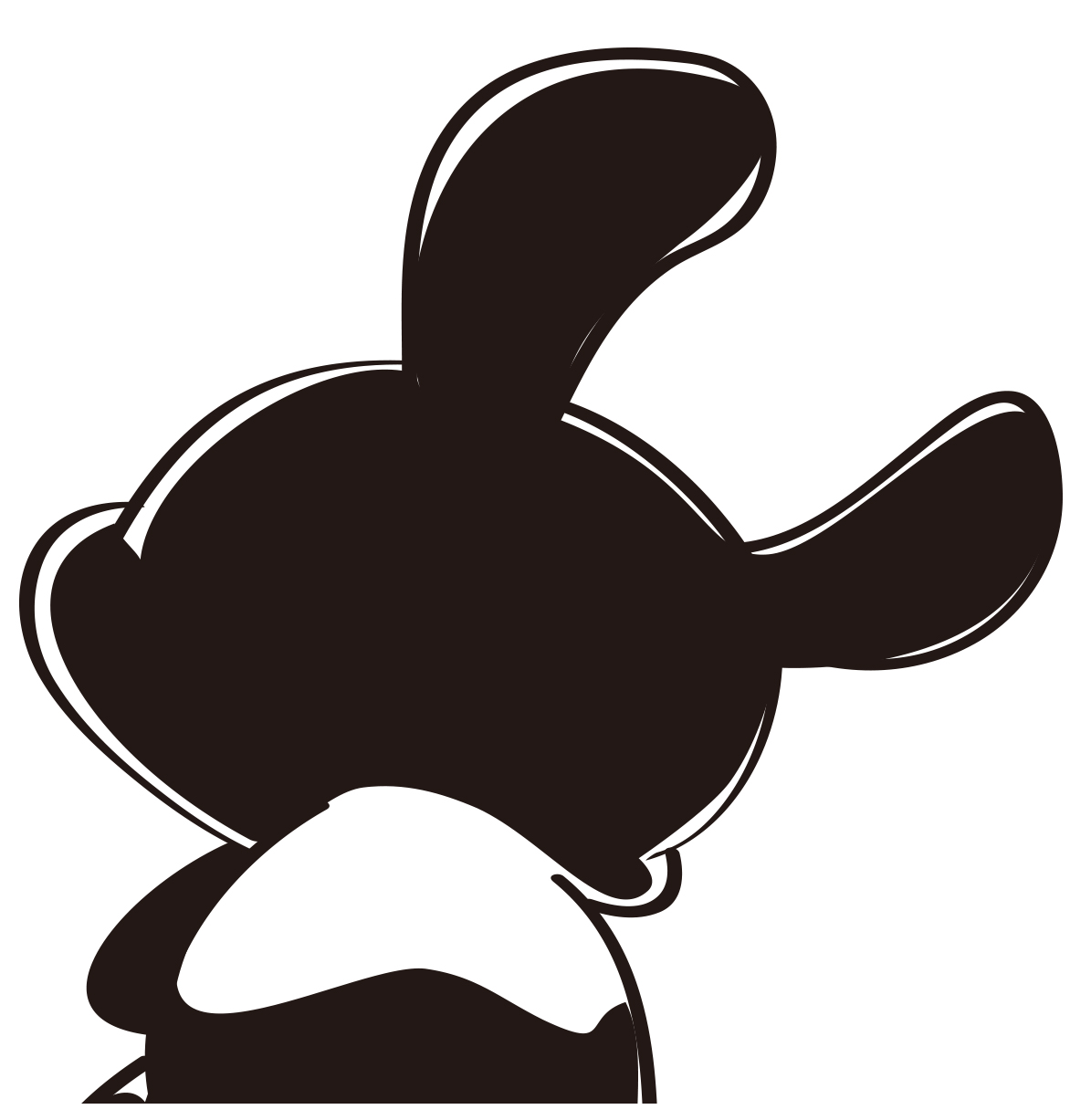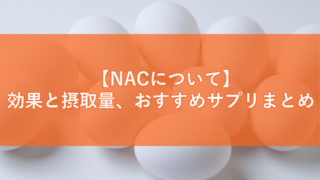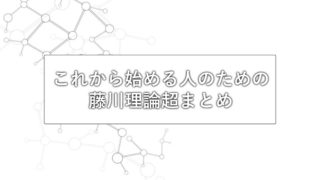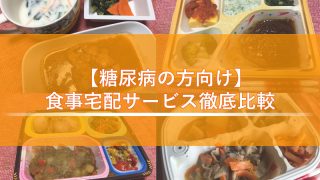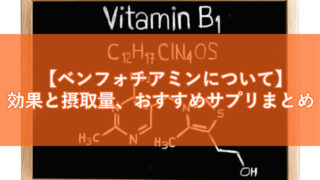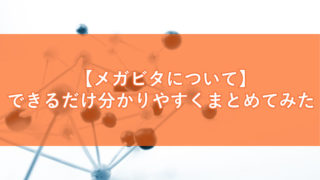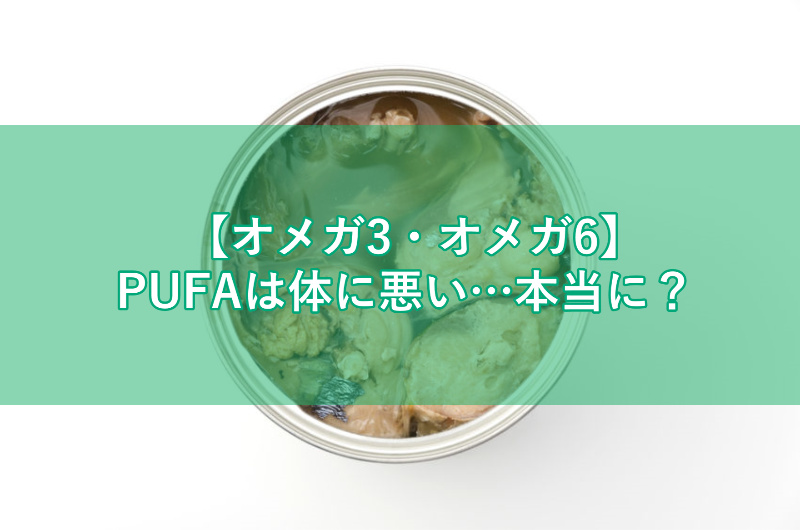
今回は前々から気になっていたPUFAについて。
『PUFAが悪い』そこから派生して『糖質制限は危険である』という主張もあって、ずっと情報を追っていた部分ですが、ひとまず自分の中で結論が出たのでまとめておきます。
PUFA悪玉論について
そもそもPUFAですが、
PUFAとは:
多価不飽和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid)の略で、オメガ3、オメガ6のことを指す。オメガ3はDHA、EPA、αリノレン酸、オメガ6はリノール酸、アラキドン酸。
オメガ3は魚油やアマニ油、エゴマ油、オメガ6はコーン油や大豆油に多く含まれる。
ここで植物油の組成が分かるので、一度チェックしておくといいでしょう。
酸化しにくいと言われるごま油や米油も割とリノール酸は多め。オリーブオイルも少なめながらリノール酸を含んでいますね。
ちなみにオメガ3は一般的に体にいいと言われています。参考にEPAについて。

PUFAが体に悪いという話
きっかけはこの本。
(2024/07/27 02:57:39時点 Amazon調べ-詳細)
この中でPUFAが糖尿病の原因である、という記述があります。どういうことなのか本の内容を簡単にまとめると、
- PUFAは酸化しやすいため優先的に代謝しようとする
- PUFAをエネルギー源としている間は糖代謝がブロックされる(ランドル効果と呼ばれる)
- 糖代謝が止まるため血中の糖が細胞内に取り込めず高血糖になる
- 問題なのは高血糖ではなく細胞内で糖を利用できなくなっている状態
というのが主張です。
ミトコンドリアで糖質、脂質は代謝されるので、どちらかを代謝している間、もう片方は代謝できない、というのはなんとなく分かると思います。
さらに
- PUFAは体温で容易に酸化され、猛毒のアルデヒドを発生させる。だから脂質代謝メインにしてはいけない、ということ
- 糖以外を燃料にした場合、甲状腺ホルモンの働きが低下し、ますます糖代謝が落ちてしまうこと
- 脂肪を燃焼した場合、糖に比べてより多くの酸素を必要とするため、脳の神経細胞が酸欠になりやすく、脳の構造・機能にダメージを与えやすいこと
さらに付け加えると、
- ケトン体が脳にいいと言われるが、脳はブドウ糖を果糖に変換して細胞内に備蓄していることが最近の研究で明らかになり、ケトン体は脂肪酸と同様に糖の代謝をブロックするため毒性物質と考えた方がよい
- 妊婦の血糖値がより高いほど胎児の成長がいいという事実がある
というのがPUFAの摂取は避け、糖質制限を止めて、糖代謝をしっかり回すために高糖質低脂肪食がいい、という主張の根拠としています。
と、僕も1回目読み終わった後は思いました。
でもちょっと考えてみると、糖質制限第1人者の江部先生は18年(2002年6月~)以上糖質制限を続けているわけで。もし上での解説が全て正しいなら江部先生はとっくに体も脳もボロボロでないとおかしい…ということになります。
PUFAの摂取は体に悪い…本当に?
ただおかしいと思いながらも、どこでどう矛盾があるのかまとめきれないでいたら、カスタマーレビューでの指摘がありました。
酸化した不飽和脂肪酸が身体にとって有害であることは理解できます。
だからといって、不飽和脂肪酸の摂取が有害であるというのは飛躍のしすぎです。不飽和脂肪酸は酸素が存在する状態で、自己酸化してしまうとのこと。
もちろん、酸化ストレスがあっても酸化していまいます。
体内における、自己酸化と酸化ストレスにおける酸化、どちらが優位に不飽和脂肪酸を酸化させるのでしょうか。
もし、自己酸化が無視できるほど軽度だったとしたら、酸化ストレスを減らせば、それに応じて酸化する不飽和脂肪酸も減るはずです。
つまり、不飽和脂肪酸が酸化するのは、必要があってのことで、単なる酸化ストレス処理工場であるかもしれません。次に、食品として酸化した不飽和脂肪酸を摂取したらどうなるかということについてです。
小腸から吸収されてしまうとのことですが、その実験はネズミの実験です。
そもそもネズミはそれほど多く脂肪酸を食べないはずです。
ヒトおける、酸化した不飽和脂肪酸の吸収度合いはまだ明らかにされていないはずです。ついでに糖質制限も否定しています。
ケトン体が心血管疾患を引き起こすということですが、遵守率が低い中の研究ですし、難治性てんかん患者さんでの報告です。
そもそも生理学的に、ケトン体には心筋保護作用がありますし、心筋細胞の主な栄養源は脂肪酸・ケトン体です。
ケトン体が危険だから糖質制限はあぶないというのは、今現在説得力がありません。まとめますと、
・身体内での酸化した不飽和脂肪酸が、自己酸化なのか、酸化ストレスによるものなのかはっきりしない
・酸化した不飽和脂肪酸を食べるとヒトではどうなるのかはっきりしていない
以上の2点が不明確なため、本書の内容は根底から崩れる恐れがあります。
マウスの実験をもって糖質制限を批判する理論は結構あります。まだ論文の精査はちょっとできないので、色んな人の意見や考えを参考にして見ていきたいところ。(いずれは自分で精査できるようになりたいですが)
またPUFAは体内で容易に酸化する、というのも本当なのか?というのもあります。
簡単に酸化してしまうなら、EPAやDHAが血液脳関門を通ること、DHAが網膜や神経、心臓、母乳や精子に多く含まれるのもおかしいし、そもそもエネルギー源としてではなく『エイコサノイド』という局部的に働くホルモン様物質の材料になる、という側面もあります。(だから必須脂肪酸と呼ばれる)
ちなみに
糖質の問題は置いておいて、PUFAの酸化はそんなに問題があるのでしょうか。脳や網膜などの神経組織、心筋などには大量のDHAが含まれます。もっとも酸化しやすいはずのDHAがこれらの大事な部位に含まれているのはなぜでしょうか。
実はDHAを大量投与しても、これらの組織における過酸化脂質はほとんど増えないことが報告されています。
これはビタミンEやグルタチオンなどの生体内抗酸化物質がある程度までPUFAの酸化を防いでくれているためです。
引用:ダイエットの理論と実践
血中で酸化しやすいというのは本当かもしれないし、酸化からくる問題はあるかもしれません。が、こう見ていくとPUFAは悪で摂取を止めるべき、というのは行き過ぎで、これも量の問題と言えそうです。
…とこの記事をまとめていってる中、最近Twitterで疫学者がこの問題について触れていたので紹介。
オメガ6の脂肪酸が身体に悪いという話は眉唾です
🔹70年代、80年代の研究を基に論ずることもありますが、それはトランス(オメガ6)脂肪酸と混同されたり
🔹オメガ3と比較して酸化されやすいとか身体に悪いという論も・・続 #栄養学 #栄養疫学 https://t.co/nBAzEEUwGR
— 🍏今村文昭🔥 (@nutrepi) September 5, 2020
🧠脳細胞でのω3, ω6 脂肪酸の濃度・・貴重な研究…
⚖️対照死亡者群と比べ、アルツハイマー病暦をもち亡くなった方はω6(アラキドン酸、リノール酸)の濃度が低かった(詳細略)📊#PLOSMedicine, 2017, .. fatty acid metabolism in the brain and Alzheimer… https://t.co/cfqurowF7B
— 🍏今村文昭🔥 (@nutrepi) September 23, 2020
PUFAに関するヒトでの研究はまだまだ少ないようです。
他にも有益なTweetをされているのでチェックしてみてください。
以上を踏まえると、PUFAの摂取が危険である、というのは説得力がないのでは?というところ。もちろん量が多いのは問題になりそうですが、摂取自体を徹底して避ける必要があるかは疑問です。
それに飽和脂肪酸が多いほど死亡リスクが高く、不飽和脂肪酸(PUFA)が多いほど死亡リスクは低下するという研究もあります。
なので合わせて糖質制限は危険だ、というのもPUFAを原因とした話では説得力に欠けるというのが今の所の僕の中での結論です。ケトン体が危険というのも説得力ないですし。
ただ他の側面から糖質制限が危険である、という話はあるので、そっちは勉強していってる最中です。(結局は量の問題で糖質制限というより『断糖』が危険という話っぽいですが)
そもそも糖質制限でPUFAの摂取量は増えるのか?
Tweetもちょっとしたんですが、そもそも糖質制限でPUFAの摂取量はそれほど増えないはずです。
糖質をカットする以上、脂質の量を増やしてエネルギー源とするんですが、その時に推奨されているのは肉の脂、バター、アボカドといった飽和脂肪酸。炒め油も推奨はオリーブオイルやバター、それとせいぜいラードぐらい。
一応魚の油はオメガ3でPUFAですが、積極的に魚食べようとは特に言ってないし、よほど意識して摂らない限り、魚からのPUFAも増えないはずです。
飽和脂肪酸は増えても、PUFAが顕著に増えるか?というと、逆にオメガ6であるリノール酸の摂取量は減る可能性が高いのでは?と考えています。(揚げ物の頻度、外食の頻度が相対的に減るため)
揚げ物の頻度なんかは太っている人向けの話なので、元々痩せている人はまた別で、結果的に増えている可能性はあるかもしれません。ただそれでも顕著にPUFAの量が増えるか?というとそんなはずはないのでは?という話です。
ちゃんと勉強せずに主食を抜けばいい、ぐらいの感覚で糖質制限をやってると、コンビニや外食の加工食品に含まれるPUFAを摂って、摂取量が増えるケースはありそうですが…。
ただし過量摂取は避けたい
ということでPUFAは危険、糖質制限は危険というのはこの理論だと説得力にちょっと欠けるのでは?というのがここまで。
ただオメガ6、特にリノール酸の過量摂取が良くないのは確かなので、炒めものはオリーブオイル(もしくはバター)。揚げ物や加工食品の頻度はなるべく減らす、というのは意識しておいた方がいいでしょう。(当たり前と言えばそうなんですが)
合わせて酸化を防ぐビタミンE、グルタチオンの材料になるNAC、αリポ酸あたりを摂っていれば、PUFA(特にオメガ3)の摂取が問題になることはなさそうです。
まとめ
ということで簡単にまとめると…
- PUFAそのものが危険というのは行き過ぎでは?
- 同時にPUFAを理由に糖質制限が危険というのも行き過ぎではないか
- そもそも糖質制限でPUFAの摂取量は顕著に増えないはず
- ただしリノール酸の過量摂取には気をつけたい
というところでしょうか。
PUFAは悪で摂取を止めるべき、というのは糖質は悪で断糖すべき、というのと同じような理論に感じます。どちらもPUFA、糖質とひと括りにせずに、こういうものは減らした方がいい、逆にこういうのはある程度OKなのではないか、みたいな研究がもっと進んで欲しいですね。
個人的に果糖に関してはもっと研究が進んで欲しいと思います。砂糖…は精製されてるから別(ビタミンやミネラル不足に繋がるため)として、黒糖とか果物、はちみつからグルコース+フルクトースを摂取することで糖代謝を改善する、という理論は破綻していないし、実際に臨床もあるようなので、もっと臨床と研究が進めば糖尿病改善に役立つのでは、と期待しています。
それとPUFA以外の糖質制限に関する話は別記事にまとめている最中です。今回触れていない甲状腺ホルモン、脂肪肝、耐糖能なんかも含めて調べているのでお待ちを。
補足情報
PUFAの本筋とはズレるので、上で触れなかった補足情報を。
1,『砂糖で治す』は高糖質でもでんぷん質はNGとしている
(2024/07/27 02:57:39時点 Amazon調べ-詳細)
この本では高糖質、特にグルコース+フルクトースの組み合わせである砂糖で糖代謝を回すのが健康の基本だ、とされています。ただ勘違いしてはいけないのは、でんぷん質、つまり米やパン、他に芋類なんかもインスリンを大量分泌させるためNGとなっているんですね。
特に穀物、豆類など日常的に摂取しやすいでんぷん質はエンドトキシン(内毒素)を発生させるため避けるべき、という主張です。(種子類、ナッツも食物繊維が多いため過量摂取はNGとしている)
糖質制限批判だからといって、糖質全てOKと言ってるわけではないので、ちゃんと何を言ってるのか把握するの大事ですね。ややこしいけど。
2,『糖質制限』の定義の曖昧さの問題
今回調べていく中で一番感じたのは『糖質制限』の定義の曖昧さ。ケトも高たんぱくも、断糖も、主食を食べてる緩め糖質制限も、広い意味では全て『糖質制限』。
『糖質制限』という言葉を使っていても、どれほど制限しているのか、総カロリーはどの程度摂っているのか、PFCバランスはどうだったのか、何を食べて何を避けたのか、詳しく見ていかないと、全く違う食事内容を指している場合は多そうです。
それとここは推測でしかないんですが、糖質制限かつカロリー制限になっているのでは?という『糖質制限』も割と存在するように感じます。(体脂肪率が5%以下まで落ちてる、客観的に見ると病的に痩せている等)
3,EPAを摂るならイワシ缶やサバ缶を
調べている中で盲点だったのは『干物』なんかは酸化してしまっているからオメガ3摂取には不向き、という情報。考えれば酸化してるってすぐ分かるんですが、アジの干物とか好きだったんでちょっと残念。
サバ缶とかもその後火を通すと一緒なんで、なるべくそのままで。この本に載ってるサバ缶サラダが美味しかったんでおすすめしときます。(青じそと玉ねぎを和えてマヨを添えるだけ)
(2021/07/05 03:02:55時点 Amazon調べ-詳細)
玉ねぎで臭みも感じず、青じそでさっぱり。マヨじゃなくポン酢でさっぱり食べるのとかもいいかも。
5,糖代謝の話はビタミンやミネラルの要素も大きく関係してくるはず
ここでは、というか糖質制限の話になると、糖質、脂質の量や割合が話の中心になるんですが、ミトコンドリア代謝を回すのならビタミンB群やマグネシウムが重要な要素になってくるはずです。糖を制限か、脂質を制限か、みたいな単純な話では終わらないでしょうね。
この辺はメガビタ要素ですが、B群やC以外に糖代謝に関わるマグネシウムや亜鉛は積極的に(サプリでもいいし食事からでも)摂るようにしておくのが良さそうです。